小学生のうちに「善悪」を教えるべき理由とは?
こんにちは☀︎
真夏になり、カブトムシの季節がやってきましたね☺︎
最近はまだ樹液の香りが少ないような気もしますが、そろそろ出てくるのでは…?と、今か今かと楽しみにしています♪
さて、そんな遊び心いっぱいのまさき先生ですが、指導中は「3回ルール」を設けています。
|注意しても同じことを繰り返してしまった場合、3回目には先生が叱るよ
というルールです。
これは、最初から強く叱ってしまうと、子どもは「なぜダメだったのか」を考える前に、ただ怖いという感情だけが残ってしまうからです。
この考え方は、日々の指導を通して強く実感しています。
子どもたちにどうすればルールを理解し、守れるようになるか?
そのヒントが、今回のテーマにもつながってきます。
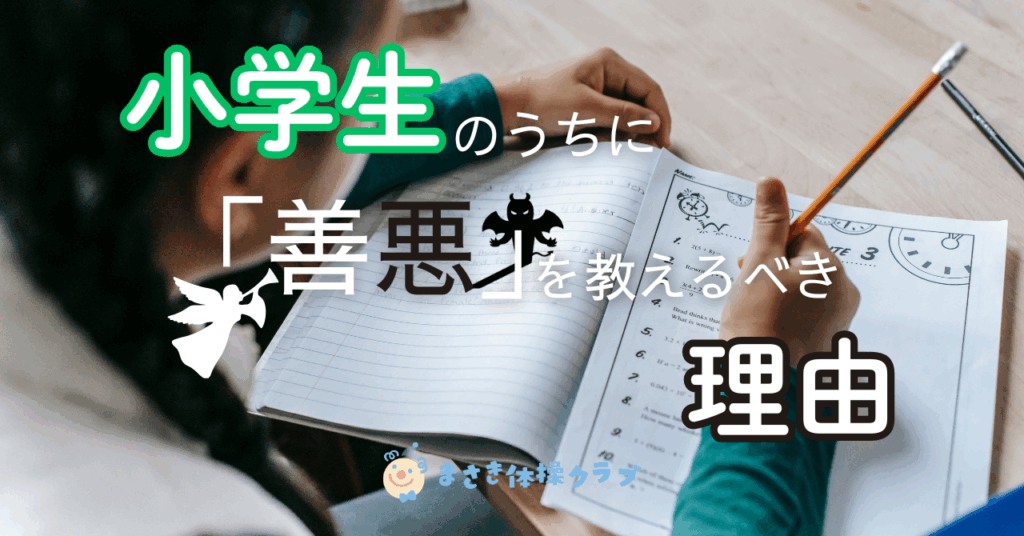
本題:「善悪の判断」は低学年までに伝えよう!
「善悪の判断は、できるだけ低学年のうちに教えた方がいい」
こんな話を耳にしたことはありませんか?
僕もブログなどで何度かお伝えしていますが、今回はその理由をシンプルにまとめてみました✨
✔️なぜ、低学年が大事なのか?
「これはダメ」「これは良いこと」と判断できるようになるには、
最初に外からの働きかけ(注意・言葉・経験)によって学ぶ必要があります。
子どもは、生まれながらに「人に迷惑をかけてはいけない」とは理解していません。
でも――
周りから注意されたり、絵本を読んだり、親や先生の話を聞いたり…
そうした日々の積み重ねの中で、少しずつ「していいこと・ダメなこと」がわかってくるんです。
これは体験しないと身につかない大事な学び。
「叱る」「褒める」だけでなく、実感させることが大切です。
🧠脳の発達も関係している!
「善悪を判断する力」は、脳の前頭前野という部分が深く関わっています。
この前頭前野は、およそ5〜7歳ごろに急成長します。
この時期にたくさんの“良い”“悪い”を体験することが、その後の行動や考え方に大きな影響を与えるのです。
つまり、「いいこと・わるいこと」の両方を、バランスよく経験させることがとても大事!
指導者や大人側も、中途半端に褒めたり叱ったりせず、きちんと区別をもって接する必要があります。
感情に任せて怒ったり、いきなり強く叱ったりしないよう注意しましょう。
📘 学校教育でも大切にされている
文部科学省でも、「低学年では善悪の基礎をしっかり育むことが大切」と明言しています。
実際、小学1〜2年生の道徳の授業では、
「してよいこと・してはいけないこと」
「ルールを守ることの意味」
などを重点的に学ぶようになっています。
こうしたルールを学ぶことが、自分自身を守る力にもつながるのです。
たとえば、救急車が来たら道を開ける。ゴミは家に持ち帰る。
日本では当たり前のように行われているこうした行動こそ、善悪を学んできた証ではないでしょうか?
実は、保護者のみなさんが日常の中で自然にしている行動が、子どもたちにとっての「道徳の教科書」になっているんです✨
そんな日本に生きていることが、僕はとても誇らしいと感じています☺️
📝 まとめ
「善悪の判断」は、できるだけ低学年のうちに伝えてあげましょう。
・脳の発達(前頭前野)と深く関係している
・心の土台をつくる大切な時期
・「いいこと」「ダメなこと」を体験から学ぶ
この時期に、たくさんの“心の学び”を積み重ねていくことで、
その後の子どもたちの成長に大きな差が生まれます😊
以上、みんなが笑顔になれる教室の裏側からお届けしました〜!👋✨
★
最後まで読んでくださりありがとうございました!
まさき体操クラブでは、[YouTube]や[Instagram]で日々のレッスン風景やイベントの様子などを発信中です。
よかったら、のぞいてみてくださいね (^-^)
体験レッスンやご入会のご相談は、[公式LINE]からお気軽にどうぞ!
スタッフ一同、お会いできるのを楽しみにしています♪
